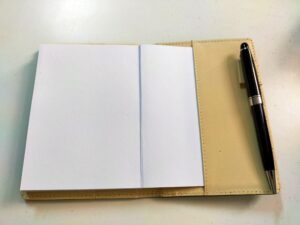誰と書く?縁ディングノート③ ~大切な人と紡ぐエンディングノート~
はじめに
協会理事の髙橋美春です。
本年もよろしくお願いします。
前回①でひとりで書く縁ディングノート②でみんなと書く縁ディングノートのお話をしました。
今回は大切な人と「紡ぐ」縁ディングノートです。
多数セミナーを開催したり、講師の皆さんを育成する立場になり
「〇〇さんに書いてもらいたいのだけど書いてもらうにはどうしたらいいのか」というご相談をたくさん受けます。
まず自分で書いてみることを当協会でも推奨しています。
自分で書いてみると、たくさんの気づきがあると思います。どういうところで詰まりやすいのか、何があったら、初めの一歩より手前、半歩進めるのかがわかると思います。
さて、3回シリーズで書いてたコラムもこれが最後です。
1回目、2回目はひとりで書く、みんなで書くだった縁ディングノート、
今回は大切な人と「紡ぐ」縁ディングノートです。
1.最初から上手に書ける人はいない
著者は2011年に市販のエンディングノートを書き始めましたが、最初は書店に並んでいるものを購入し書き始めましたが、かなり苦戦し、完全に書ききることができませんでした。
市販のノートは、本人の情報も調べないとわからないことが多かったり、財産のことなどから始まるノートも多くみられます。これでは書けないとなるのも頷けます。
現代社会では、とかく、書くという機会が減っています。
暑中見舞いのかもめーるは2020年に廃止、年賀状は昨年販売分から値上がりし年賀状しまいされた方も多いでしょう。季節の手紙を書くこともなくなり、今や文書はパソコンを使うのが殆どでしょう。
筆を持ち、文字を認める(したためる)ことが少なくなった今、書くこと、言葉にすること、文章にすることのハードルがあがっているのです。
著者自身、当初は書ききれなかったものの、縁ディングノートの効能を知り、必要性を感じました。そこで、2012年からは、見よう見まねで手帳に縁ディングノートを書くようになり、今では毎年の恒例行事のひとつになっています。
この自身が感じた書きずらさを活かし、セミナーでは「冊子は薄く中身は厚く」をモットーに参加者さんが楽しく取り組めるように工夫しています。
2.縁ディングノートは誰のもの?
セミナーでは毎回「お名前・日付」を書くことをお願いし、「縁ディングノートは誰のものですか?」と聞いています。
この質問のお答えで一番多いのがご家族など「大切な方のもの」というものです。
表紙に名前書いてくださいね、とお願いしているにも関わらず、「誰かのためのもの」と思われている方が多いのです。
最初から、縁ディングノートは誰かのためにかくものだと思うと途端にハードルがあがり、ただでさえ書くことから離れている方が、さらに書きづらくなってしまうのです。
縁ディングノートは状況や気持ちが変化したとき、できれば定期的に更新してほしいと思っています。これは内容そのものの変化に備えてということもありますが、最初から完成版を作らなくて良いということなのです。書き換えることを前提に、気楽な気持ちで取り組んでほしいと思います。
当初、セミナーでは、まずは「自分のため」に書いてみましょう。とお伝えしていますが、そうすると皆さん肩の荷がおりたような、ホッとしたお顔をされるのです。
3.自分のために縁ディングノートを書こう
自分のための縁ディングノートのポイントは、自分の棚卸です。
縁ディングノートは自分の取扱い説明書でもあるわけですが、一番近くに一番長い時間一緒にいる自分のことは意外とわかっていないものです。セミナー内ではこの棚卸を一緒に取り組んでいきます。自分自身をみつめ、棚卸することでご自身の縁ディングノートの土台が完成します。
ご先祖様を10代遡れば1024人のご先祖様がいます、と当協会でもお話していますが、20代遡ると1,048,576人、30代遡ると10億人を超えます。
セミナー内でもご先祖さまを辿って戸籍をとり、感謝が芽生えたら、お墓参りに行きましょうとお話しますが、お墓に行く前に確かなのが、自分自身なのです。10代なら1,024人、20代なら104万人、30代なら10億人は、自分の中に必ず流れています。
縁ディングノートは自分のために、自分を大切にするために書くことこそ、大切な人と紡ぐ縁ディングノートの始まりです。
まず自分のために書いてみて、これは遺したい、これは伝えたいがでてきたら、それをしたためる、それでよいと思います。
自分を大切にできない人は他人も大切にはできません。
まずはご自身のために自分の中にある大切な人と、縁ディングノートを紡いでみてください。
著者は一般向けの講師としてもセミナーを全国各地、様々な形で多数展開しています。
一度は参加者として縁ディングノートセミナーを受講されたい方はお気軽にお声かけください。
(文責 理事 髙橋美春)