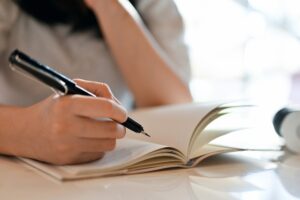相続における縁ディングノートの役割
1、筆者の失敗談
筆者は約10年間相続業務の実務を行ってきたのですが、開業当初から現在に至るまで、生前の相続対策の相談となると遺言書の相談が多いように感じます。「相続でもめないための対策」=「遺言」と考える方が多いのでしょうか。そして相談者の多くは、こういう遺言書を書きたい、遺言書の書き方を教えて欲しいと言って来られる方が多いです。
開業当初は相談者の話を聞いて、遺言書の案文のみを作成して相談者が納得して帰る。こんなことを繰り返していました。ただこの相談者とのやりとりに疑問を感じることが筆者自身多くなっていきました。
この相談者の問題点は果たしてこれだけなのだろうか。相談者が自分の相続の他の問題に気づけていなくて、その情報を引き出せてないのではないか。遺言の案文を作るにしてももっと違う情報があれば内容が大幅に変わってきていたのではないのかなど様々な疑問が生じてきました。
例えば相談者の家族関係、相続財産の中身だけでなく、相談者である親自身が今まで自分の家族や周りの人間とどのように関わってきたのかの情報、相談者の子に対する想い、きょうだいに対する想い、お世話になった方への想いなど、相談者の心の奥底にある想いを丁寧に正確に確認したらもっと質の高いサービスを提供できる。そう感じ、相続対策の相談に来た親に縁ディングノートを書いてもらうことを始めました。
実際縁ディングノートを書いてもらってじっくり相談者の話を聞くと、相談者との距離が今まで以上に縮まっていることに気づきました。今ではもっと早くこの縁ディングノートを活用していたらと思って後悔しています。
2、相続における縁ディングノートの役割
相続対策を始める手順はまずは現状分析。この現状分析に最適なツールが縁ディングノート。つまり相続対策のスタートは縁ディングノートを書くところから。そして縁ディングノート書いてもらうことが相続対策で一番大事なことだと筆者は感じています。もちろん縁ディングノートだけでは不十分ですが、縁ディングノートを基礎の土台として、それにどのような相続対策を追加して積み上げていくのか。遺産分割対策、認知症対策、納税資金対策、節税対策のどれを相談者が希望しているのか、あるいはどこに相談者自身が気づいていない問題点があるのか。縁ディングノートの先にある次のステップが見えてくるのは、この縁ディングノートでしっかり現状分析ができているから。そして縁ディングノートのいいところはあまり難しいことを考えなくても一般の方でも書ける内容になっていて、とっかかりやすいところです。
3、終わりに
相続対策は何から始めたらいい?相続対策でやった方がいいことは?相続でもめないためにはどうしたらいい?と聞かれたら筆者は今なら迷わず縁ディングノートを各ことからと答えます。財産だけでなく想いを次世代に引き継いでいくこと。縁ディングノートを書くことによってこの目的が達成でき、縁ディングノートを書くことが相続で一番円満に行く方法だと確信しています。
【筆者プロフィール】
菅井 之央(すがい ゆきお)
取得資格:司法書士、行政書士、縁ディングノートプランナー、上級相続診断士、FP2級、薬剤師
趣味:けん玉
岐阜県中津川市出身。広島市安佐北区というところで司法書士・行政書士事務所を開業しています。相続コンサルタントとして、相談者の真の悩みを聞き、相談者自身では気づけない問題点を浮き彫りにして、悩み・問題点・不安などを解消するお手伝いをしています。「縁ディングノート書き方講座」をはじめとして、年間20~30件の相続セミナーを開催しています。
著書に「相続・終活コンサルティング事例集2025」など計5冊あります。
お問い合わせ先
司法書士行政書士菅井事務所
事務所所在地:広島市安佐北区口田4-1-8-201 事務所HP:http://www.shihosugai.jp/
電話番号:082-962-4683
メールアドレス:sugaijimusho@shihosugai.jp